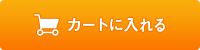どろぼう一門?
立川流という落語会のインディーズにあって、個性と研鑽を競うなかでも、いまや立川流四天王と称される、立川談笑。
ときに、その思いきった古典改作の手法には目を剥くご通家もあるかもしれません。
それでも、そんなボーダーを往還する噺をつくりあげるためには、愛して止まない落語にたいする周到な研究があるはずです。
もちろん、談笑師匠が声高にそんなことを語ることはありません。
いつもチャーミングな高座がわたしたちの前にあるだけです。
「落語研究室」では、そんな談笑師の魅力的な落語の秘密に迫りながら、毎回楽しいおしゃべりが繰り広げられます。
研究員は、談笑師のほかに、年間350回も落語会に足を運ぶという聴き巧者の広瀬和生さんと、三味線の技量とユニークな個性で落語会にひっぱりだこの寄席囃子方の恩田えりさん。
広瀬さんの的を射て軽快な問題提議で、談笑師が大いに語ります。
※毎回締め括りは、えりさんの演奏で名人の出囃子をお楽しみください。
さて、第15回の研究テーマは〈泥棒〉です。
「夏泥」「出来心」「締め込み」「転宅」……と、
研究員がつぎつぎに挙げていく泥棒噺ですが、
どうにも、泥棒をやりそこなう間抜けな泥棒ばかりです。
「芋俵」「鈴が森」ときて、あまりにばかばかしい他愛のなさに
談笑研究員も思わず「中身がないなあ、泥棒噺!」と嘆息。
それこそ落語らしさでもあり、噺家の腕の見せどころなんですね。
あまり泥棒噺はやらないという談笑師ですが、
かつて「だくだく」を現代に移植して演じたことがあります。
舞台は、なんとホームレスの世界。
人間の業を訴追する立川流では、可愛い泥棒は活躍しにくいようですが
「談笑噺で泥棒もやってほしい」と広瀬さん。
今回は、談笑研究員の前座時代の研鑽が目に見えるような、
お宝の書き込みノートがスタジオに持ち込まれ、一同感嘆!
故・小さん師匠から盗んだ「間抜け泥棒」が小さな文字でびっしり!
えりさんのエンディングの演奏は、いつもの気だるいマクラで
「うちは泥棒一門」と言い切った柳家喜多八師匠の出囃子「梅の栄」です。
■「立川談笑の落語研究室」は、毎月第2・第4金曜日に配信されます。
第16回の研究テーマは「黄金餅」です、どうぞおたのしみに!
《携帯電話・スマートフォン(iPhone、Xperia等)、通信機能内蔵タブレット(iPad、GALAPAGOS等)、通信機能内蔵音楽プレーヤー(iPodTouch等)等へは「ダウンロード及び保存」はできません。お手数ですがパソコンでダウンロード後、お手持ちのデバイスへ同期頂き、お楽しみください。》