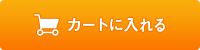〝だれに向けて書くのか〟 with 岡 敦 客員教授
天才コラムニスト・小田嶋隆のライティング講座は、
文章のスキルは当然として、ライティングに必要なすべての要素を伝授する全6回。
「言葉の運営について、いまいちど考えなおすという作業は、
書くのが商売の人間ばかりでなく、小学生から横町のご隠居まで
普通に生活する誰にとっても、けっして無駄にはならないはず」
毎月1回100分間の小田嶋せんせいの講座と、逸材の客員教授との45分間の対談。
* * * * * * * * * * * * *
第3時限めのテーマは、ターゲット・読者です。
1/3:
不特定多数、特定多数、不特定少数、特定少数という4つの場に向けたとき、それぞれ書き方が違います。
誰に向かって、何を書くのか。対象を考えて書くことの意味は。
読み手が誰であるかを意識して書くと、書き方そのものが自分のなかで意識化できるのではないか。
ということで、今回は宛名を明確にした手紙を書いてもらいました。
原稿や手紙など文章を書くということは、第一義的には読み手に情報なり感情なり思いなり、
何かを伝えることだという建前になっていて、小田嶋先生も、それはそのとおりとしながらも、
「文章というのは情報を運ぶ船みたいなものですから、そこにどんな情報が乗っているのか、
どう伝えるのかというのが主目的なんだけれども、私はそれは表向きの目的であって、
実際の効果あるいは福音とでも言うべきか、それは………」
「手紙という形式で書くと、べつの形式で書いた場合には出てこない、自分の内面の
かなり奥深くにある変なものが出てくる可能性がある。
自分のなかに埋もれていた感情を発掘できたときは、ちょっと成功なんですね」
2/3:
休憩をはさんで、物を書こうとする人には大いに参考になる受講生からの質問回答。
そして、あらかじめ受講生がメーリングリストに提出した「手紙」の課題をとりあげて
実践的で具体的な実習が展開されています。
手紙の宛先は、古い友人だったり、優しかったおばあちゃんだったり、思い出の土地だったり、
その多様さゆえに、文体もまた何通りもの変化を見せました。
3/3:
客員教授対談は、作家の岡 敦さん。
小田嶋せんせいとの共著が3冊もあるクリエイティブ・ディレクイターの岡康道さんの弟さんで
非常に優秀な中学生だった時代から、ちょっと踏み外した高校生だった時代から、そして
大きく道を踏み外していた(という)大学生の頃からいろいろよく知っている幼馴染でもあります。
誰もが知っているけど誰も読んでいない?本流の哲学や文学の古典を真正面から独自に
読み解いた瞠目の著書『強く生きるために読む古典』が私たちの胸を打ちます。
「言葉自体には意味なんてないわけで、結局言葉って文脈で意味が決まるじゃないですか、
言葉の塊である本だって、どういう文脈に置かれるかによって意味が違ってくる。
面白いとかつまらないとか、どういう文脈で読まれるかで違うわけです」(岡)
「なんか、敦の〝治療過程〟みたいな本だったよね、あれは(笑)」(小田嶋)
■この音源は、2014年3月20日にリアル授業を収録したものです。
■コラムがコラムであるためのスピリットと効能を知るオリエンテーションと、
第1時限、第2時限も、下記配信中!
http://www.radiodays.jp/item_set/show/718
http://www.radiodays.jp/item_set/show/719
http://www.radiodays.jp/item_set/show/728
《携帯電話・スマートフォン(iPhone、Xperia等)、通信機能内蔵タブレット(iPad、GALAPAGOS等)、通信機能内蔵音楽プレーヤー(iPodTouch等)等へは「ダウンロード及び保存」はできません。お手数ですがパソコンでダウンロード後、お手持ちのデバイスへ同期頂き、お楽しみください。なお一部(聞く教科書・聞く聖書)DRM付きWMA音源がございますが、DRM対応の携帯音楽プレーヤー以外では再生できません。》