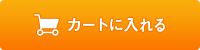「ゆとり教育」はほんとうに間違いだったのか?
最近の大手メディアは、「わかりやすさ」と「単純化」の区別がつかなくなっています。複雑な問題を「YESかNOか」「賛成か反対か」といった二分法に還元し、「スピード感」を演出することで拙速に答えを出そうとしています。
「月刊 中島新聞」では、「単純化」と「スピード感」に徹底的に抗いたいと思っています。
敵を見つけバッシングし、あっという間に忘れてしまう現代に、異なる視点を導入したいと思っています。
本当のわかりやすさとは何か?
今、じっくり考えてみなければならないテーマとは何か?
なかなか大手メディアが取り上げないテーマに切り込みながら、今最も話を聞いてみたいゲストをお呼びし、議論を深めます。
* * * * *
今月のゲストは、寺脇 研さん。
文部科学省で大臣官房審議官を務めた元官僚で「ゆとり教育」を推進した中心人物として知られています。また、現役官僚時代から映画に精通し、数々の映画評論を発表されてきました。現在は京都造形芸術大学で教鞭をとっていらっしゃいます。
「ゆとり教育」は近年、様々な形で批判され「脱ゆとり」が政府の方向性として示されています。ゆとり教育というと、学力低下の温床とされ、授業時間の減少や教科書が薄くなったことなどが問題だとされます。
しかし、本当にゆとり教育という方向性は、間違えていたのでしょうか?
寺脇さんが強調するのは「学習の動機づけの獲得」です。高度経済成長期は、人生の物語が明確でした。「いい学校を卒業し、いい会社に勤め、終身雇用・年功序列で定年を迎え、老後は年金暮らし」というモデルが、安定した人生のレールでした。しかし、この物語はもはや通用しません。日本型経営は瓦解し、雇用の不安定化が拡大しています。
旧来の物語が崩壊状態の中、いくら旧来型の受験戦争モデルで子供たちの学習意欲を高めようとしても、それは不可能でしょう。「いい大学」に入ることが、必ずしも「いい人生」につながるという保証はどこにもないのですから。
寺脇さんの志したことは、新時代に適応した多元的動機づけを確保する教育体制の整備でした。金太郎飴的な均質的教育ではなく、子供の多様性を尊重することで学習意欲を高めるというのが、重要な指針でした。
また、学習は一生涯にわたるもので、子供・若者だけに限定されないという「生涯学習」というコンセプトを構築し、政策化をすすめてきました。地域と学校がクロスし、多元的な学びの機会を担保する「コミュティスクール」も、寺脇さんが推進しようとしてきた政策です。
このような「ゆとり教育」は、保守思想とも合致します。個人の均質化を問題視し、コミュニティにおけるトポスの獲得を重視する保守思想家は「ゆとり教育」のコンセプトにこそ賛同すべきでしょう。
しかし、保守を自称する人々は、かつての「思い出」にすがるばかりで、終焉した高度経済成長期の物語から抜け出せていません。保守は「漸進的改革=保守するための改革」こそ進めるはずですが、多くの人が「ゆとり教育批判」を展開しています。これは保守思想の空洞化の結果でしょう。
今回は、寺脇さんとともに「ゆとり教育」のコンセプトを、じっくりと振り返りつつ、今後の展望を議論しました。また、寺脇さんが民主党政権で力を入れた「新しい公共」の問題にも、議論は及びました。
今回の番組を聞いていただければ、「ゆとり教育」が目指した本質がクリアになると思います。
◎今月の時評コーナー
「TPP問題」について、ガンディーのスワデーシー(自国産愛用)論を切り口に
論評しました。
■今月の書評■
1920年代・30年代の顛末が、現在の日本社会の動向を探るときに重要だと考え、
下記の2冊を取り上げてお話ししました。
筒井清忠『昭和戦前期の政党政治:二大政党制はなぜ挫折したのか』(ちくま新書)
岩田規久男編『昭和恐慌の研究』(東洋経済新報社)
中島岳志
Video streaming by Ustream
《携帯電話・スマートフォン(iPhone、Xperia等)、通信機能内蔵タブレット(iPad、GALAPAGOS等)、通信機能内蔵音楽プレーヤー(iPodTouch等)等へは「ダウンロード及び保存」はできません。お手数ですがパソコンでダウンロード後、お手持ちのデバイスへ同期頂き、お楽しみください。なお一部(聞く教科書・聞く聖書)DRM付きWMA音源がございますが、DRM対応の携帯音楽プレーヤー以外では再生できません。》